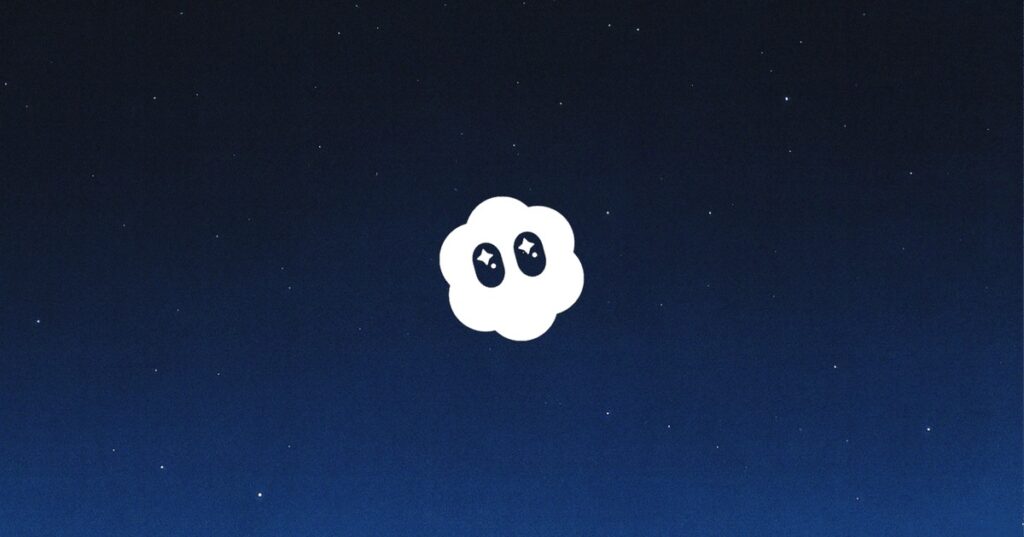人工知能の進化がもたらす感動と驚きの裏で、ひとつの倫理的爆弾が炸裂した。OpenAIの最新映像生成モデル「Sora2」が登場してからわずか数週間、その高精度な映像生成力は世界を席巻した。だが同時に、「故人の復活」という新たな問題をも浮き彫りにしたのだ。
それは、マイケル・ジャクソンとロビン・ウィリアムズが街角で即興パフォーマンスを繰り広げる動画がSNSで拡散された瞬間から始まった。映像は驚くほどリアルで、まるで彼らが本当に蘇ったかのよう。しかしこの“奇跡”は、遺族にとって悪夢だった。
ロビン・ウィリアムズの娘、ゼルダ・ウィリアムズは、SNS上で強い怒りを表明した。
「お願いだから、もう父のAI動画を送らないで。そんなことは誰も望んでいないの。これは彼を、私たちを、そして人間そのものを侮辱する行為よ。」
彼女の言葉には、深い悲しみと苛立ちがにじんでいた。AIによって父の姿が再現されるたびに、過去の痛みがえぐられる。しかも、それを“エンタメ”として楽しむ人々がいるという現実が、彼女をさらに追い詰めている。
この発言は瞬く間に世界中に拡散し、AIがどこまで人間の領域に踏み込むべきかという議論を巻き起こした。中には「肖像権は死後も保護されるべきだ」と訴える声がある一方、「AI時代の新しい表現の自由」として擁護する意見も根強い。しかし、いずれにせよ“死者をコンテンツ化する”という行為が持つ倫理的な重みは、無視できないものとなった。
ロビン・ウィリアムズは、即興演技と温かいユーモアで世界中に笑いを届けた名優だ。『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』『いまを生きる(Dead Poets Society)』など、彼の演技は今も多くの人の心に刻まれている。しかし2014年、彼は長年のうつ病と戦いながら、静かに人生の幕を閉じた。
それから11年後、AIによって再び“命を吹き込まれた”彼の姿がインターネットに現れる。だがそれは、芸術的な復活ではなく、誰かのクリックを稼ぐための見世物だった。
AI生成されたロビンの映像では、彼が自らを茶化すように「俺はもうこの世にいないのに、またツアーに出てるよ!」と笑う。皮肉な冗談のように見えるが、その背後には、人間の尊厳をどこまでAIが模倣できるのかという深い問いが潜んでいる。
娘のゼルダはさらに強く訴えた。
「父の人生を“似ている”というだけで再構成して、操り人形のように動かすなんて、芸術でも創造でもない。そんなものは、人間の歴史を歪めた“過加工のホットドッグ”よ。」
この痛烈な比喩が象徴するのは、AIが“人間の記憶”を素材として消費する危うさだ。AIによる創作は、いつしか死者の人生までも素材化してしまう。
OpenAIはこの問題に対して迅速に声明を発表した。
「歴史的人物の描写には表現の自由が伴いますが、私たちは公人やその家族が自らの肖像利用を管理できる権利を尊重します。特に、亡くなった著名人については、遺族や管理団体がSora上での利用停止を求めることが可能です。」
これは、AIの自由と人間の尊厳のバランスを取るための第一歩といえるが、根本的な解決にはまだ遠い。
さらに、米映画協会(MPA)会長チャールズ・リフキンも厳しい姿勢を示した。
「Sora2の登場以来、著作権侵害動画が急増している。OpenAIは“近く制御機能を提供する”と述べているが、それでは不十分だ。侵害を防ぐ責任は、コンテンツホルダーではなく、プラットフォーム運営側にある。」
AIの創造力が無限に拡張する一方で、著作権と肖像権の境界はますます曖昧になっている。
Sora2は、リリースから数日でApp Store無料アプリランキング1位を獲得し、ChatGPTを凌駕する勢いを見せた。
人々は“文字から映像を作る魔法”に熱狂した。しかしその熱狂の陰で、誰かの心が傷ついている。
AIが描く世界がどれほど美しくても、人間の痛みを見落とした創造は、やがて醜い現実に変わる。
ゼルダの言葉が象徴するように、「AIが人の形を借りて語ること」と「人間の記憶を穢すこと」は、紙一重だ。
もしAIが故人の声を再現できるなら、それは愛する人をもう一度抱きしめる奇跡にもなり得る。だが、誰かのクリックを稼ぐための素材として使われるなら、それは死者の尊厳を奪う暴力にほかならない。
Sora2の進化は止まらない。だが今、私たちが見つめるべきは“どこまで作れるか”ではなく、**“どこで立ち止まるべきか”**なのだ。
AIが生み出す未来をどう制御するか。
その答えを探すのは、AIではなく、私たち人間自身である。