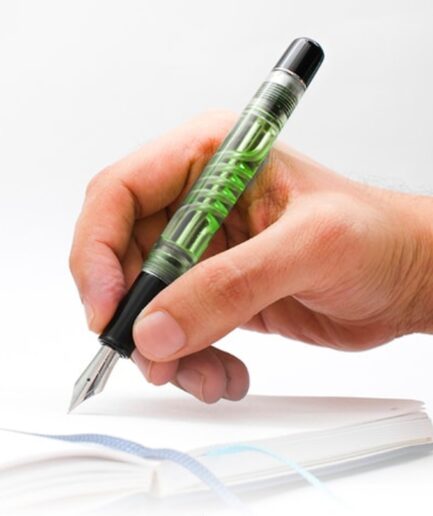テーブルトップRPGやボードゲームの世界において、ダイスは単なる道具ではなく、物語を紡ぎ、冒険に命を吹き込む存在です。『Honest Dice』は、その”核”とも言えるダイスに、新たな誠実さと革新をもたらすプロジェクトです。
Kickstarterで2,000人以上の支援者を集め、目標額の40倍以上となる40万ドル以上の支援を獲得したこのキャンペーンは、単なるクラフトプロジェクトではありません。これは、金属加工と数学、そして遊び心が融合した、まさに「信頼できる」ダイスづくりへの挑戦です。
制作者であるFlying HorseDuck(本名:David)は、以前から人気のあった自身のポリヘドラル(多面体)ダイスを、今回はアルミニウムとチタンという高品質な金属を用いて製造。設計・製造のすべてにおいて徹底した精度と美学を追求し、単なる装飾品ではなく、ゲームプレイにおいても実用的で、公平性を備えた製品となっています。
Honest Diceの特徴
まず注目すべきは、すべてのダイスが精密機械加工(CNCマシン)によって削り出されている点です。これは通常のキャストや3Dプリントでは実現できない、緻密で滑らかなエッジ処理と、寸分の狂いもない形状を保証するもの。数値的なバランスも計算されつくしており、ダイスがランダムにかつ公平に転がることに重点が置かれています。

このプロジェクトの核となるのは、「誠実さ(Honesty)」という思想です。ダイスは本来、確率に基づくフェアな判定を支える道具であるべきですが、市販品の中には重量バランスや数値配置が偏っているものも少なくありません。そこでHonest Diceでは、数値配置における数学的な対称性とバランスを徹底的に分析し、すべての面が均等に出やすい設計が採用されています。D20のような多面体においては、数値の偏りがゲーム性に大きく影響しますが、本製品では各数字の配置が互いに均等な対角関係を保ち、出目に偏りが出にくい設計がなされているのです。

素材には、軽量で加工精度の高いアルミニウムと、強度と耐久性に優れたチタンを使用。アルミモデルは軽快な転がりと持ち運びやすさを、チタンモデルはその重厚感と高級感が特徴です。チタン製のダイスは特に、プレイヤーの手元で確かな存在感を放ち、コレクションとしての価値も非常に高いといえるでしょう。

さらにデザイン面でも独自性が際立ちます。とりわけ注目されているのが**“Hex d4”**という、六角形をベースにした新しいd4(4面ダイス)の形状です。従来のピラミッド型d4は転がりにくく、読み取りにくいという欠点がありましたが、この新デザインは視認性・転がりやすさ・手触りすべてを向上させた革新的なフォルムです。

加えて、全てのダイスには目の配置にフォントや視認性への工夫が施されており、暗い場所や素早いゲームプレイの中でも数値が即座に読み取れるよう設計されています。また、ナンバリングの刻印も深く、長年の使用でも摩耗しにくい点も嬉しいポイントです。
カラー展開や仕上げのバリエーションも豊富で、光沢のあるポリッシュ仕上げや、落ち着いたマットなサンドブラスト仕上げなど、プレイヤーの好みに応じた選択が可能。高品質な収納ケースも用意されており、持ち運びや保管もスマートに行えます。
このように、見た目の美しさ、物理的なバランス、使いやすさ、すべてにおいて一切の妥協がないプロダクトこそが『Honest Dice』なのです。
将来性
このプロジェクトが単なる一回限りの試みではないことは、支援者数や反響の大きさからも明らかです。ダイス市場は、いわゆるTTRPG(テーブルトップ・ロールプレイングゲーム)の再ブームとともに再注目されており、とくに高品質な金属製ダイスの需要は年々増加しています。
David(Flying HorseDuck)は過去にも複数のダイス系プロジェクトを成功させており、今回の『Honest Dice』は、彼の製品哲学がひとつの完成形に達した証といえるでしょう。また、今回のプロジェクトが実現すれば、将来的には新たな面数の展開や限定エディション、プレイヤーとのコラボ企画なども期待されており、コミュニティとの継続的な関係性が見込まれています。
特に注目すべきは、設計そのものがオープン性と透明性を重んじている点。制作者は数値配置やバランス理論についても積極的に情報発信しており、支援者が「なぜこのダイスが公平なのか」を理解できるように配慮されています。こうした姿勢は、単なるガジェットの域を超え、誠実なものづくりとして高い評価を受ける理由でもあります。
今後の展開としては、TTRPG業界やボードゲームメーカーとの連携、限定版のリリース、教育用途での展開(数理バランス教材としての可能性)など、さまざまな方向性が考えられるでしょう。