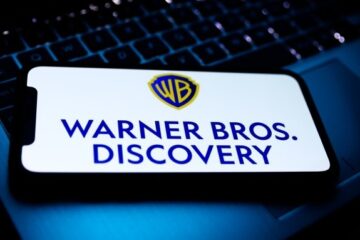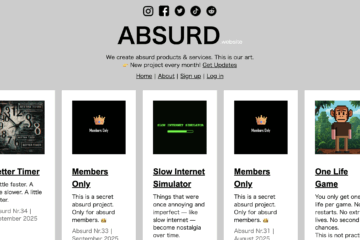新聞やオンラインメディアにとって、Google検索からのアクセス流入は生命線です。ところが今、その流れが大きく変わろうとしています。原因は、検索結果ページの上部に表示される「AI Overviews(AI要約)」。ユーザーは記事をクリックせずとも、要点だけをその場で把握できるようになり、結果として出版社のサイト訪問数が激減しているのです。
たとえば、女優ソーチャ・キューザックがBBCドラマ『Father Brown』を降板したニュースは、これまでなら大手紙のウェブ版で大きなトラフィックを生んでいたはずです。ところが、リーチ社(The MirrorやDaily Expressの発行元)によれば、今年に入ってからは期待通りのアクセスを得られなかったといいます。その理由がまさにAI要約でした。読者は記事に飛ぶことなく、検索ページの要約で満足してしまったのです。
出版社が抱える深刻な懸念
オックスフォード大学ロイター研究所のフェリックス・サイモン博士は、「AI要約は読者が記事へクリックする必要を減らし、その結果として出版社に不利益が及ぶ」と指摘します。実際にデイリーメールなどを抱えるDMGメディアは、クリック率が最大で89%も減少したと競争・市場庁(CMA)に報告しています。
リーチ社のデビッド・ヒガーソン氏は、次のように憤ります。
「我々出版社が正確で信頼できる情報を提供している。Googleはそれを燃料として動いているのに、リターンはどこにあるのか?」
AI要約は読者のクリック需要を減らし、出版側に何の経済的利益ももたらさない。まさに「情報の創造者ではなく流通業者が利益を独占している」状態なのです。
次なる脅威「AIモード」
さらに懸念されているのがGoogleの新機能「AIモード」。これは検索結果を会話形式で表示し、リンクを従来より大幅に減らすものです。もしこれが主流になれば、業界への打撃は計り知れないとヒガーソン氏は警告します。
バウアーメディアのSEO責任者スチュアート・フォレスト氏も、「ここ10年、Googleは検索画面に独自機能を増やし続け、ユーザーが外部サイトに行く必要を薄めてきた」と分析。今は影響が顕在化していなくても、「ユーザーがAI要約に慣れれば、間違いなく大きな課題になる」としています。
Googleの反論と出版社の模索
もちろんGoogleはこの批判に真っ向から反論しています。広報担当者は「他社以上にトラフィックをウェブに送っている」と強調し、検索経由のクリック数は「前年とほぼ安定している」と説明。さらに検索の質も改善し、AI要約によって長く複雑な質問が増え、結果的にリンクの露出機会が広がっていると主張しました。
しかし出版社側は納得していません。独立系パブリッシャー連盟やNPO団体フォックスグローブなどは、CMAに法的措置を求める申し立てを行いました。Googleが出版物のコンテンツを「不当に利用している」とし、暫定的な規制を導入すべきだと訴えているのです。
同時に、メディア各社はAI要約にどう取り込まれるかを試行錯誤しています。最適化されたコピーを用意し、自社が引用されるよう工夫する一方で、WhatsAppやニュースレターといった独自のチャネルを育てる戦略にもシフト。リーチ社は「自社ブランドに直接触れてもらう仕組みを強化する」ことが今後の鍵だと語ります。
結論:クリック減少時代をどう生き抜くか
AI要約の登場は、オンラインメディアにとって大きなターニングポイントです。「クリック=収益」の構造が揺らぎ、情報流通の主導権がGoogleに集中するなか、出版社は新しい読者接点の開拓を迫られています。
この流れを単なる脅威とみるのか、それとも進化への契機とするのか。出版業界にとって、まさに生存戦略が問われる時代に突入したといえるでしょう。