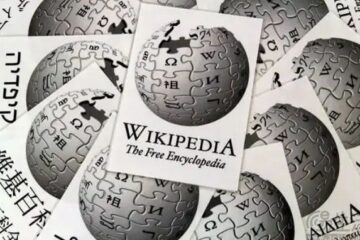母を殺害し、その死を覆い隠すためにAIで母親の声を偽造した娘。この恐るべき事件は、南米エクアドルで起きた実話だ。現地警察が「AIが共犯になった」と評したこの事件は、テクノロジーと倫理、そして人間の闇が交錯する新たな時代の到来を告げている。
母の名はマルタ・セシリア・ソリス・クルス(Martha Cecilia Solis Cruz)。49歳の弁護士で、仕事にも家庭にも真面目な女性だった。10月6日、彼女の失踪届が出される。しかしその後も、家族のスマホにはマルタ本人の声で送られてくる音声メッセージが届き続けた。穏やかで優しい声。「心配しないで、元気よ」。誰もが安心した。だが、それは――AIが作った幻影だった。
十日後、警察が家を捜索したとき、洗濯機の中から彼女の遺体が発見される。遺体は六つに切断され、青いプラスチックのバケツに詰められていた。犯人は、なんと彼女の実の娘、アンドレイナ・ラモタ・ソリス(Andreína Lamota Solís)。そして、行方不明の母親を装い、家族や警察を欺くために使われた音声――それは、アンドレイナがAIで生成した“母の声”だった。
彼女は母親の声紋データをAIに学習させ、何十もの音声を合成した。メッセージはまるで本物のように自然で、母のイントネーションや息づかいまでも再現されていた。さらには、母親の服を着て外出し、防犯カメラに“母が生きている”ように見せかける周到さまで見せた。映像の中では、長い髪、花柄のワンピース、黒いサングラス――。しかしその「母親」は、すでにこの世にはいなかった。
警察の捜査が進む中、アンドレイナの自宅からは200GBにも及ぶデータが押収された。その中にはAI音声の生成履歴、トレーニング用素材、アプリの記録、さらには他の失踪女性のクレジットカードまでが含まれていた。捜査官ガロ・ムニョス(Galo Muñoz)は報告書でこう記した。
「彼女は冷酷で、精密で、強い支配欲を持っていた。AIは彼女の道具ではなく、彼女自身の延長だった。」
事件の全貌が明らかになるにつれ、社会全体が震撼した。AIは殺人を犯していない。しかし、真実を覆い隠す「共犯」になった。十日間、マルタはAIの中で「生き続け」、家族も世界もその幻を信じた。音声だけでなく、映像までもが現実を欺き、真実を十日間も遅らせたのだ。
この事件が突きつけたのは、単なるAIの悪用ではない。「真実」と「偽り」の境界がいとも簡単に壊される現代の脆さである。警察は、聞こえてくる声を信じ、映像を信じ、デジタルの証拠を頼った。しかし、それらすべてが「生成された現実」であったとしたら、人間は何を信じればいいのか。
米国FBIは2024年に発表した報告書でこう警鐘を鳴らしている。
「AIによる音声・映像の偽造は、被害者が経験的に真偽を見抜けないほど精巧になっている。」
詐欺事件では金が奪われる。しかしこの事件では、真実そのものが奪われた。
さらに問題を複雑にしているのは、AIが法的に「共犯」とみなされるのかという問いだ。アンドレイナが母親を殺したのは事実だが、AIが生成した音声や映像は、法律上どのように扱われるのか。多くの国では、これに明確な答えを持たない。
EUの「AI法案(EU AI Act)」では、AIを「リスクレベル」に応じて分類している。しかし「音声クローン」や「ディープフェイク」など、現実を偽装する技術は依然として法のグレーゾーンにある。アメリカでも、2024年に「Deepfake Accountability Act(ディープフェイク説明責任法)」が州レベルで提案されたが、対象は主にエンタメや情報操作であり、刑事事件までは踏み込めていない。つまり、今回のようなケースでは、AIによる「嘘」そのものが罪になるのかどうか、誰にも判断できない。
技術は中立だ。しかし、人間がその中立性を“嘘”のために使ったとき、AIは人間の冷酷さを拡張する鏡となる。アンドレイナのAIは、母の声を模倣しながら、同時に人間の倫理を嘲笑っていたようにも思える。
警察が事件報告の最後に残した言葉が、全てを物語っている。
「アルゴリズムには感情も悔恨もない。
それはただ命令を実行し、幻を維持するだけだ。」
この言葉は、AI時代に生きる私たちへの警告でもある。AIが「声」や「姿」を再現できるようになった今、人類はどのように「真実」を定義し直すべきなのか。未来の犯罪は、もはや血の跡を残さないかもしれない。そこにあるのは、コードと信号、そして完璧に偽装された“存在”だけだ。
マルタの死は終わりではなく、始まりだ。私たちは今、AIが「感情を模倣できる時代」に足を踏み入れている。問題はAIではない。それをどう使うかを決める人間の心だ。
AIは罪を犯さない。だが、人間がAIを使って嘘をついた瞬間、真実は人間の手からこぼれ落ちる。