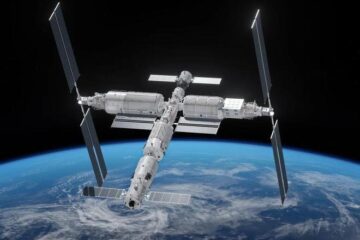人間の最もプライベートな空間――トイレ。
その場所が、今や「次世代の健康診断室」になろうとしている。
衛浴の老舗ブランド、Kohler(コーラー)が発表した新製品「Dekoda(デコーダ)」は、たった一つの小さなカメラでこの常識を覆した。価格は599ドル(約9万円)。だが、それは単なるトイレアクセサリーではない。あなたの健康を“見る”マシンなのだ。
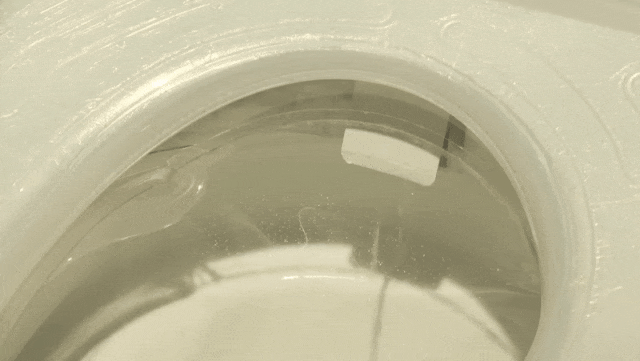
かつて日本のTOTOが「温もり」と「清潔」をトイレに持ち込み、生活の質を高めたように、KohlerはAIの力で“健康”という新しい価値をトイレに注ぎ込もうとしている。座るとカメラが静かに起動し、尿や便の色、形状、流速、含水率を解析。結果はアプリに即座に送信され、体の水分バランスや腸内状態、炎症の可能性を自動で診断してくれる。異常な色調を検知すれば「もしかすると血尿の兆候かもしれない」とアラートを出す。

つまり、Dekodaは“排泄物という日常のデータ”を“健康という洞察”へと変換する、最も自然で最も親密なウェアラブルデバイスなのだ。
Kohlerの野心はそこにとどまらない。
複数のユーザーが同じトイレを使っても問題ないよう、指紋認証システムを搭載。誰が座ったかを自動判別し、それぞれの健康履歴を個別に記録する。
しかも、DekodaはバッテリーでもUSBでも駆動可能。設置も容易で、AIが撮影する範囲は「マクロ的に便器内のみ」。ユーザーのプライバシーを守るため、カメラの角度は固定され、データはエンドツーエンドで暗号化される。

それでも、カメラ付きトイレという言葉には、やはり心理的な抵抗がある。
「AIにお尻を見られているようで落ち着かない」という声も当然上がるだろう。
しかしKohlerは言う。「私たちは“見る”のではなく、“分析する”のです」と。
この分野にはすでに新興企業も次々と参入している。
米オースティンのスタートアップ「Throne(王座)」は、“Artificial Gut Intelligence(人工腸知能)”というAIシステムを開発中だ。
便や尿の色、質感、速度、粘度を多次元的に解析し、肠内環境や代謝、脱水の兆候まで把握できる。2026年1月の製品化を目指しており、投資家には元ツール・ド・フランス王者のランス・アームストロングの名前もある。
彼がかつて睾丸癌を克服したことを思えば、この分野に注ぐ情熱にも納得がいく。

だが、AIトイレの発想は決して新しいものではない。
すでに10年以上前、スタンフォード大学の故サンジブ・ガンビール教授が、肛門の「肛紋」で個人を識別する“スマートトイレ”の研究を進めていた。

彼のチームが考案したトイレは、尿流速度、便の粘度、排泄時間を解析し、さらに尿試験紙モジュールで感染症や腎機能障害、膀胱がんの兆候を検出するという、まさに「分子生物学×AIのトイレ版CTスキャン」だったのだ。

それは決してジョークではない。肠内には人体の細胞数を上回る1,000兆以上の細菌が存在し、それらは消化だけでなく、免疫、代謝、そして感情にまで影響を与えている。
便や尿は、その生態系の“日記”だ。つまり、トイレの中には、健康を語る膨大なデータベースが眠っている。
現代医療では、排泄物の分析から炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)や、大腸がんの早期兆候を見抜くことができる。
米国癌協会の報告によれば、「排尿習慣の変化」だけで特定の癌の発見につながるケースも少なくない。
AIトイレの狙いは、診断ではなく“気づき”にある。病気になる前に、日々の変化を掴む――それが本当の目的だ。
もちろん、プライバシーの壁は厚い。KohlerもThroneも「撮るのは便器の中だけ」と繰り返し強調する。映像データは自動で匿名化され、クラウド送信前に暗号化。HIPAA(米国医療データ保護法)にも準拠している。
Throneのエンジニアはこう語る。「私たちは“個人”を見ない。“腸”を見るんです。」
一方で、日本のTOTOはまったく異なるアプローチを取る。
彼らの最新モデルにはカメラは一切ない。代わりに、便座の下にLED光学センサーを設置し、排泄物の反射光を解析して形や色、量を推定する。

しかも、英国発の「ブリストル大便分類法」を基準に、便を七つのタイプに分けて分析するという。
アプリと連携し、便の履歴を**“排便カレンダー”として可視化。食生活や運動データとも組み合わせ、ユーザーに具体的な生活改善提案を行う。
それでも、この市場には大きな課題が残る。光環境の違い、誤検知、カメラの汚れ、多ユーザー識別の精度など、家庭というリアルな現場では多くの変数が存在する。
さらに、商業的にも、DekodaやThroneのようなAIトイレは本体価格に加えて年間70〜150ドルのサブスクリプション費用が必要となる。
多くの人にとって、それは「なくても困らない贅沢品(Nice to Have)」であり、「絶対に必要なもの(Must Have)」ではない。
しかし、その見方もすぐに変わるかもしれない。高齢化が進む社会で、日々の健康データを自動で記録する仕組みは確実に求められていく。心拍を測るスマートウォッチが当たり前になったように、近い将来、「トイレがあなたの主治医になる」時代が来るのかもしれない。
なぜなら、トイレだけは“使わない”という選択がないからだ。その「必ず使う」という日常性こそが、最大のアドバンテージになる。
Dekodaが投げかけた問いは、一見ユーモラスでありながら極めて現実的だ。
「巨頭(Kohler)は売り出した。あなたは座る勇気があるか?」
それは単なる好奇心ではなく、テクノロジーと人間の関係を問う哲学的な質問でもある。私たちはどこまで機械に体を預け、どこまで自分のデータを信じるのか。その答えは、案外、あなたのトイレの中に隠されているのかもしれない。