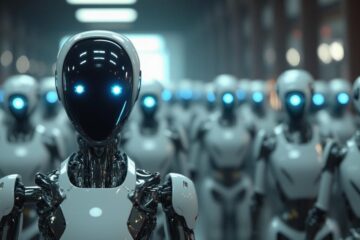技術があっても、“後ろ盾”には勝てない?
AIの物語の第一章が「技術革命」だったとすれば、第二章の主題は、どうやら「権力のゲーム」になりつつある。
かつて香港映画界では、映画を作る人は皆“背景(コネや後ろ盾)”を持っていると言われていた。そのため、俳優や監督は多くの場合、自由がきかず、映画業界の競争も“背景”のぶつかり合いだった。
今のAI業界も、それに似てきている。
Google、Microsoft、Meta、ByteDance、Tencent、Alibabaといった大手企業が火花を散らす戦場。TikTokは自社の圧倒的なトラフィックを使って「豆包(Doubao)」を猛烈にプッシュし、Googleは社全体のリソースを投入してGeminiを各種アプリに猛プッシュしている。
こうした巨大企業の力の前では、ManusやOpenAIのような優れた企業ですら、抗いきれないのだ。
2025年11月以降、それまで後れを取っていたGoogleは、性能面・ユーザー数ともに急速にChatGPTに追いついた。特にマルチモーダル領域では、OpenAIを上回り、様々なベンチマークで首位に立っている。OpenAIのサム・アルトマンも、Googleの台頭が自社に大きなプレッシャーを与えていると公言している。
かつて世界的に注目された汎用AI「Manus」も、単独での戦いをあきらめ、インターネット大手Metaに買収される道を選んだ。KimiやDeepSeekのような人気AIも、今では豆包や元宝といったサービスの圧倒的なトラフィックに押しつぶされている。
この“親の七光り”の世界では、超巨大企業だけがゲームに参加できる。
ビジネスの世界では、「小が大を打ち破る」物語がよくある。たとえGoogleやApple、Tencent、Alibabaといった巨大企業であっても、時には小さなスタートアップに敗れることがある。しかし、AIの分野ではそうした話が非常に難しくなっている。
技術力だけでは足りない、“資源”の力
芸能界では「タレントは露出さえすれば売れる」という言葉がある。今のAI業界も、まさにこの状態だ。
ChatGPTはチャットボットの発明者であり、Appleがスマートフォンを発明したような存在。技術もブランドも、ずば抜けていた。
しかしGoogleという超巨大企業が本気を出すと、ChatGPTはすぐに圧力を感じ始めた。Geminiは複数の機関によるベンチマークでGPTを上回り、アルトマンは社内文書で「技術的リードが縮まっている」と警鐘を鳴らし、「今後の市場環境は相当厳しいものになる」との見通しを示した。
中国市場では、「豆包」がすでにKimiを抜いて月間アクティブユーザー数でトップとなっている。DeepSeekを搭載した「元宝」も、すでにDeepSeek単体のユーザー数を上回っており、DeepSeekの成長は、元宝というエコシステムの恩恵を受けた結果ともいえる。
なぜこれほどまでに強いのか?答えは明らかだ。背後にGoogleやByteDanceといった大企業がついているからだ。
確かに、AI系のスタートアップにも大企業や大資本からの投資はある。手元に多額の資金やリソースもある。だが、巨大企業の持つ“エコシステムの優位性”は、スタートアップには再現できない。
例えば、GoogleはGeminiをAndroidに直接組み込み、スマートフォンのデフォルトアシスタントにしている。GoogleはChromeという世界一のブラウザを持ち、Gmailという巨大なメールサービスもある。MicrosoftのCopilotも、Officeスイートに直接統合されている。
こうした日常的に使うアプリとの深い統合により、ユーザーは使いたくなくても使うことになる。そして実際、体験は非常にスムーズだ。
Kingsoft(WPS)やMicrosoftのように、オフィスソフトにAIを組み込む事例もある。Tencentは元宝をWeChatに組み込んでおり、ユーザーは新しいアプリをダウンロードする必要すらない。
たとえAIの導入が少ないAlibabaやAnt Groupであっても、AlipayやQuarkといった有力なプラットフォームがある。
こんな環境を、OpenAIやManus、Kimiといった企業がどうやって真似できるだろう?自前でスマホOSやWeChatを開発しろというのか?
AIというビジネスは“他力”に依存しすぎている
一部のビジネスは、自力でなんとかなる。miHoYoは数本の大ヒットゲームで二次元ゲーム分野の覇者となり、NetEaseやTencentでもその躍進を止められなかった。
しかし、AIは違う。外部との連携が深すぎるビジネスなのだ。
第一に、AIは資産が非常に重い。インターネットサービスで最もコストがかかるのは通常「トラフィックの購入」だが、AIの場合、数千億円規模のインフラ投資が必要だ。自宅やマンションで開発できるものではない。
第二に、使用場面がエコシステムに強く依存している。他の製品との連携なしでは活用できない。
たとえば、Manusは機能的には非常に強力だが、個人ユーザー向けには単独で動けない。ブラウザやWebサービスへのアクセスが必須であり、チケット予約などにはアカウント認証や支払いが必要だ。しかし、これらの機能を制御しているのはGoogleやApple、WeChatのような巨大企業である。
Manusがやろうとしているのは“システムレベルの仕事”だが、“システムレベルの権限”がない。
いわば、「数千万の資産運用講座」を学んだ子供が、自分の家庭にその資産がないようなものだ。ブラウザやスマホOSを自社で持つGoogleのような企業が自ら参戦すれば、独立系AIエージェントの居場所はますます狭くなっていく。
AI検索も同様の問題を抱えている。今や検索は独立したアプリではなく、iPhoneの検索ボックスのようにOSに統合された存在だ。Perplexityがどれほど使いやすくても、Appleのデフォルト検索エンジンではない。Googleはこの座を維持するために、毎年200億ドルをAppleに支払っている。
中国では検索ボックスはBaiduやWeChat、スマホメーカーが支配しており、スタートアップのAI検索ツールにその席を譲ることはほとんどない。
たとえ技術力で一時的にシェアを得たとしても、次に立ちはだかる壁は「マネタイズ(収益化)」だ。
“収益化”にも“親の力”が必要な理由
裕福な家庭の子どもは、教育費を回収するのが容易だ。
例えば、子どもが「水準の低い修士号」を取得したとしても、親のコネを使って外資系銀行に就職したり、家業を継いで管理職に就ける。一方で、経済的に厳しい家庭の子どもが高い学費を払って留学しても、その学歴が評価されずに就職先が見つからないこともある。
AIの収益化を見てみると、この構図と大差ない。
同じ技術でも、それを持つのがスタートアップか、大企業かで、マネタイズの手段もスピードも大きく異なる。
たとえば、OpenAIは依然として赤字に苦しんでいるが、MicrosoftはGPTサービスを自社クラウド(Azure)とパッケージ化することで、業績を大幅に伸ばしている。今や「OpenAIサービス」は、Microsoft Azureの主力商品となっている。顧客企業は元々Microsoftのクラウドを使っているため、AI機能を“追加購入”する形で自然に導入される。
さらに、CopilotとOfficeの統合も非常に強力だ。MicrosoftはAI機能をOfficeに追加し、サブスクリプション料金を引き上げた。ユーザーは値上げを拒否すればOfficeが使えない。選択肢はない。
このモデルは、Microsoftが過去10年間に収益を拡大してきた主要戦略でもある。新しい技術や機能が登場するたびに、Microsoftはサブスク料金を調整し、それでもユーザーは便利さと価値を得られるため、不満は少ない。まさに“Win-Win”の値上げだ。
Googleのバンドル戦略 vs OpenAIの限界
C向け(個人向け)の収益化でも、GoogleとOpenAIの差は明らかだ。
GoogleはGeminiの有料プラン(月額20ドル)を販売する際に、Google One(クラウドストレージサービス)とセットにすることで、非常に魅力的なパッケージに仕上げている。ユーザーはAIだけでなく、GmailやGoogleフォトでのストレージも得られる。これは、「たとえAIを使わなくても、ストレージは必要」だから、ユーザーにとって“無駄がない”という強みがある。
もしManusのようなAI企業がGoogleに属していれば、そのサブスクリプションもこの20ドルのパッケージに含められたかもしれない。その方が、収益化もスムーズだったはずだ。
一方で、OpenAIのサブスクリプションはほぼChatGPT単体に依存している。SoraやCodexといった新しいプロダクトも、自社内で独自に展開しており、収益化のスキームは限定的だ。
ByteDance傘下の「豆包」は、さらに巧妙だ。豆包が出した回答を、そのまま短編動画に繋げることで、TikTokと同様に“広告収入”を得る構造を確立している。
さらに、豆包には「チャット内広告」という新機能もある。ユーザーが近くのレストランを尋ねると、豆包はそのままグループ購入リンクを提示し、ユーザーはワンクリックでTikTokのローカル生活サービスに遷移できる。
このような垂直統合型の商流は、Kimiのようなスタートアップには再現不可能だ。短編動画の在庫も、ローカル生活サービスの供給網も、電商の物流も、スタートアップには存在しない。
彼らはトラフィックを外部に販売するしかないが、現在のAI業界の構造では、多くのプラットフォームがAIツールに入り口を開こうとしない。仮に開いたとしても、内部エコシステムに比べてコンバージョン率が極めて低い。
スタートアップの収益モデルは“激戦”必至
そうなると、スタートアップに残された収益化手段は一つしかない。
-
B向け(法人向け)にはトークンを売る
-
C向け(個人向け)にはサブスクリプションを売る
このモデルは、ほとんどお金を払って商品を買うという、極めてシンプルな商売だ。
しかし、このモデルは競争が激しすぎる。法人ユーザーは「いくらでどれだけのトークンが得られるか」しか見ておらず、Microsoftのようにプレミアムを乗せて売ることができない。
個人ユーザー向けのサブスクも、価格がすでに“固定化”されている。20ドル、または10〜30元(約200〜600円)の価格帯が市場に定着しており、それ以上の価格を付けようとすると、ユーザー離れが起きてしまう。
価格の壁:突破は極めて困難
例えば、MiniMaxの中国国内向け製品「星野」の月額料金も、やはりこの相場に収まっている。
実際、中国国内のほぼ全てのオンラインサブスクリプションサービスがこの価格帯に集中しており、誰が価格を上げても成功しにくい。
最近、IPO(株式公開)申請を行ったAIスタートアップの「智普AI」や「MiniMax」は、非常に大きな赤字を計上している。スタートアップに赤字は珍しくないが、両社とも赤字幅が年々拡大しており、当面黒字化の見通しは立っていない。
実際には、これらの企業が特別に悪いというわけではない。たまたま上場申請を出したため、その財務状況が公開されただけだ。申請していない他のAI企業にも、もっと深刻で広範な赤字が隠れている。
OpenAIですら、ユーザー数が7億を超えていても黒字化できていないのだ。
そしてこの問題は、スタートアップが単独で解決するには極めて困難であり、最終的には“大手企業の力”を借りることになる可能性が高い。
“親を探す”小さなオタマジャクシたち
この“親の七光り”時代において、独立独歩では生き残るのが難しい。
条件が合えば、大企業への“身売り”は悪くない選択肢となる。
Metaは「Scale」と「Manus」の買収を発表し、Appleも「Perplexity」の買収を検討しているという報道が出ている。
一度買収されれば、状況は一変する。
Manusはこれまで、機能の実装には他社の許可が必要で、しかも巨頭企業の自社AIとの競争にもさらされていた。しかしMeta傘下に入れば、WhatsAppやInstagram、Messenger、Facebookといったプラットフォームに“ネイティブ統合”される。そこでは、チャットやショッピングといった機能が自由に使える。
さらに、MetaはAIハードウェアにも注力しており、ARグラスなどとの統合が進めば、ManusはSiri級の“システム権限”を手に入れる可能性すらある。
こうしたAIアプリ企業にとって、大手による買収は明確なメリットがあるのだ。
OpenAIは“親”になりたがっている
もちろん、自らが“巨頭”になる道を目指す企業も存在する。
OpenAIは、当初Microsoftに大きく依存していたが、その構造は「親子関係」ではなかった。Microsoftは最大の出資者であるが、OpenAIの経営権を持っていない。
そのためMicrosoftは、OpenAIを“実子”のようには扱わず、自社でAI製品を開発・提供している。
OpenAIも、誰かの子会社にはなりたくない。汎用AI(LLM)の先駆者として、真のテックジャイアントを目指している。
Microsoftには「Edge」というブラウザがあるが、OpenAIはそれに頼らず自ら「Atlas」というブラウザを開発している。クラウドについても、最大手のAzureではなく、自前で提携先を探して計算能力を確保し、Google Cloud Platform(GCP)とも契約を結んでいる。
明らかに、OpenAIは「GAFA」のような**“次の巨大企業”になろうとしている**のだ。
果たして、スタートアップにチャンスはあるのか?
インターネット時代において、業界に大きな変革が訪れるたびに、スタートアップが巨頭を打ち破る物語があった。
ByteDanceは、BAT(三巨頭)による支配を打ち破り、マンションの一室から世界的な企業へと成長した。
また、PinduoduoやmiHoYoのように、AlibabaやTencentといった巨大企業を向こうに回し、特定分野でトップに立った例もある。
新興分野では、柔軟さ・発想・技術力が重要であり、勝機があると信じられていた。
しかし、AI分野においてはこの“神話”が成り立ちにくい。
過去3年間で、スタートアップが持つ「柔軟性」や「先行者メリット」は、巨大企業の“物量”によって次々と打ち砕かれてきた。巨頭がシステムの“入口”を握っている限り、その力は圧倒的だ。
AIの物語の第一章が「技術革命」ならば、第二章は「権力のゲーム」である。それが、いま我々が目の当たりにしている現実なのだ。