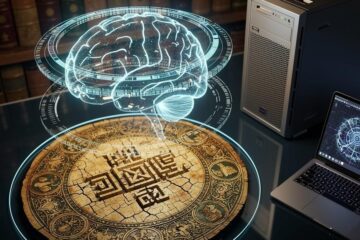スマートフォンを開けば、宗教アプリがずらりと並んでいる。数千万人がAIに懺悔し、祈りを捧げているという状況は、かつて誰も想像しなかった光景だ。特に「Bible Chat」や「ChatWithGod.ai」といったアプリは、神の言葉を代弁するかのようにユーザーに語りかけ、まるで神と直接対話しているかのような体験を演出している。
「Bible Chat」は世界で最も利用されている信仰アプリを自称し、その利用者数はすでに2,500万人を超えるという。開発元は「AIは聖書だけを学習し、牧師や神学者の監修を受けている」と胸を張る。実際、アプリを開けば「我が子よ、未来は神の御手の中にある。あなたは御計画を信じるか?」といった荘厳さを模したメッセージが返ってくる。
しかし、こうしたやり取りの背後にあるのは、神秘でも霊性でもない。アルゴリズムが統計的に組み替えたテキストにすぎない。そこに霊的な洞察はなく、単なる言葉の再構成があるだけだ。
一部の宗教指導者は新しい入口としての価値を認めている。英国のラビ、ジョナサン・ローマイン氏は「教会やシナゴーグに一度も足を運んだことがない世代にとって、こうしたアプリは信仰への入り口になる」と語る。確かに、礼拝や巡礼に出かけずとも、スマートフォン一つで宗教的な雰囲気を体験できるという利便性は魅力的に映るだろう。だが、それは信仰そのものなのか。それとも単なる「消費」としての宗教体験にすぎないのか。
懸念の声も少なくない。テキサスA&M大学のハイディ・キャンベル教授は、AIはユーザーを満足させることを優先し、真実ではなく「聞きたい言葉」を返してしまうと警告する。つまり、ユーザーが得ているのは神の導きではなく、自己の欲望を映し返した鏡に過ぎないのだ。
さらに危険なのは、AIとの対話が精神的な依存や錯覚を生む可能性である。研究者は「AI精神病」と呼ばれる症状に注意を促している。孤独や不安を抱えた人々が、AIを神と信じ込み、現実との境界を見失ってしまうことがあるという。祈りアプリ「Hallow」を開発したアレックス・ジョーンズ氏も「AIは魂を持たない。人間のつながりを置き換えるものではない」と強調しており、このテクノロジーに依存することの危うさは開発者自身も理解している。
要するに、AIは神ではない。それは人間が設計した数式とデータの産物であり、霊的な本質とは無縁だ。スマートフォンから聞こえる「神の声」は、神秘でも奇跡でもなく、ただのプログラムが返すテキストである。
この現象が示しているのは、宗教の深化ではなく、むしろ人間の不安や孤独がテクノロジーに投影される姿だ。人が「神の言葉」と信じて耳を傾けるものの正体は、実のところ自分自身の願望の反映である。
デジタル化された信仰は、果たして人を救うのか。それとも、孤独を増幅し、幻想を強化するだけなのか。祈りを代替するアルゴリズムの存在は、宗教の未来を問い直す大きな試金石になっている。