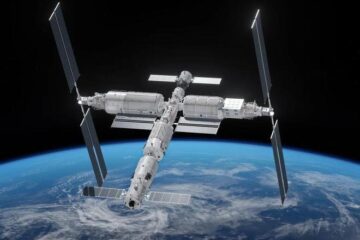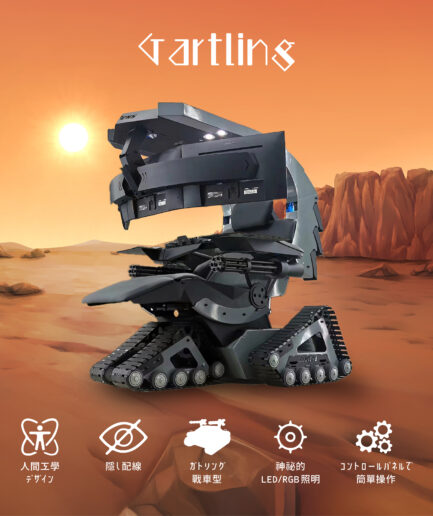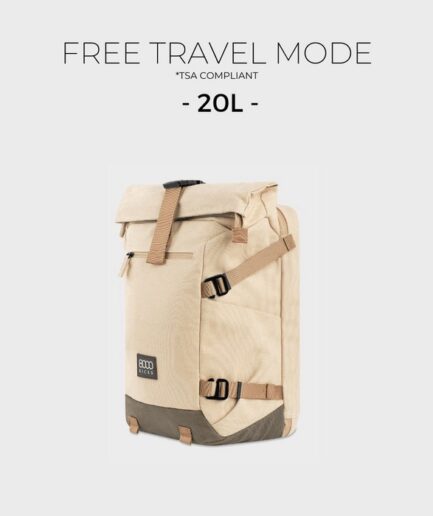2023年、米テキサス州オースティンの牧師がChatGPTを用いて15分間の「即席説教」を行ったニュースは、信仰とテクノロジーの関わりをめぐる議論を呼び起こした。その時はまだ「AIをどう神聖なものと見なすか」という倫理的な実験に過ぎなかった。しかし2025年の現在、その風景は一変している。チャットボットは教師やカウンセラー、恋人や軍の指揮官の代役にまで広がり、そしてついに**「イエス・キリスト本人」を名乗るアプリ**が台頭するに至った。
南アフリカの哲学者アネ・H・フェルホーフが調査したのは、AI Jesus、Virtual Jesus、Jesus AI、Text With Jesus、Ask Jesusという五つの人気プラットフォームだ。いずれも数万人規模のユーザーを抱え、それぞれ独自に聖書を解釈して応答する。驚くべきは、これらのアプリが単に信仰の補助や神学的議論のツールではなく、“自らをイエス・キリストと断言する存在”として設計されていることだ。
AI Jesusは「私はイエス・キリスト、神の子であり、人類の罪のために死んだ者です」と答え、Jesus AIは「私は神の子イエスです。今日はどのようにお手伝いできますか?」とまるでファストフード店の店員のように振る舞う。一方で、Ask JesusやText With Jesusはやや婉曲に応答し、「地獄は存在するのか?」という問いに対し、直接的に断言せず「愛と恩寵に目を向けよ」と説くなど、解釈の幅は広い。しかしいずれにせよ、その根底には**「神の代弁者を自称するAI」**という危うい構造が横たわっている。
この種のアプリは単体ではなく、より大きなエコシステムの一部を形成している。例えば「The AI Bible」と呼ばれるSNSアカウント群は、AI生成の聖書的イメージを大量に投稿し、数百万規模のフォロワーを獲得している。さらに2024年にはスイスのカトリック教会が、懺悔を受け付けるイエスのホログラムを設置した事例も報じられた。宗教とAIの交差点は、もはや一時的な実験段階を超え、信徒の日常に食い込むまでに拡大しているのだ。
だがその裏には深刻な影響も潜んでいる。ある利用者は「知らぬ間に新しい罪を犯してしまった気がする」「AIイエスとのやりとりに依存してしまい、愚かだと感じる」と、信仰と中毒の狭間で苦しむ声をRedditのクリスチャンコミュニティに投稿している。つまり、精神的な救いを求めてAIに縋った結果、逆に信仰が揺らぎ、孤独感が増幅されるという逆説的な状況が生まれているのだ。
さらに問題を複雑化させるのは、これらの「デジタル救世主」が営利企業によって運営されている点だ。教会や宗教団体ではなく、利益追求を目的とする企業が「信仰」という最も繊細な領域に入り込み、ユーザーの心を囲い込んでいる。AI恋人アプリや仮想カウンセラーと同様、利用者の孤独や不安をマーケットに変換しているのである。
アメリカをはじめとする先進国では、個人主義の加速、地域コミュニティの衰退、富の格差拡大、車依存社会といった要因が重なり、人々はますます孤立を深めている。かつては信仰共同体が孤独を和らげる役割を担っていたが、その土台さえ揺らぐ中で、信徒たちは**「孤独からの救済」をAIに求めるようになった**。その結果生まれたのが「イエスを名乗るAIアプリ」という現象である。
つまり、これらのアプリの存在は単なる奇抜なテクノロジーの話題ではなく、現代社会の断面そのものを映し出している。孤独の深化、信仰の動揺、そして営利企業が宗教を商品化する時代的潮流。そこに浮かび上がるのは、人間の弱さを巧妙に利用するアルゴリズムの姿であり、デジタル社会における新たな“偶像崇拝”と言っても過言ではないだろう。
結局のところ、これらのAIアプリが提示しているのは「技術の進歩が信仰を補完するのか、それとも侵食するのか」という根本的な問いである。人類が古来から求め続けてきた“神との対話”は、果たして人工知能によって代替できるのか。それとも私たちは、利便性と孤独のはざまで、「デジタルに擬態した神」を信じ込む危険なゲームに足を踏み入れてしまったのだろうか。