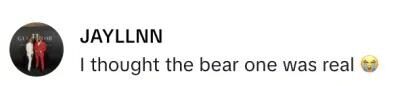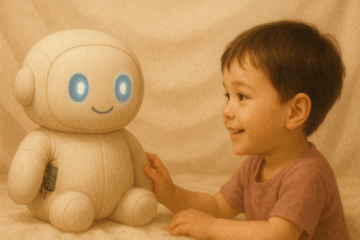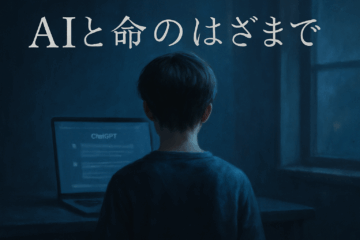かつて「AIで生成された映像」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべたのは、不自然な動きや奇妙な表情、そして何よりも“バレバレ感”だった。しかし2025年の今、その常識が静かに、しかし確実に覆されつつある。
TikTokで再生数5億回を超えた1本の動画が、それを如実に物語っている。映っているのはただの夜間監視カメラの映像。場所はとある裏庭。画面中央には一台のトランポリン、そしてその上で楽しそうに跳ね回る10匹のウサギたち。……ただそれだけ。
一見して、何の変哲もない日常の一コマに見える。だが、そこに“異変”は確かに存在した。

融合するウサギ? これは本物か、それとも…
動画を注意深く見ていた視聴者たちは、ある瞬間に気づく。ウサギが、跳ねながら突如として1匹に融合しているのだ。
これを目にした途端、視聴者の間にざわめきが走った。「これは本当に実写?」「もしかして、AIによるフェイク?」と、コメント欄は騒然。実際、編集部でも確認された通り、この映像にはロゴもウォーターマークも一切なく、パッと見では判断がつかない。
だが、あまりにも自然すぎる物理現象の不整合や、動物たちの挙動の“滑らかすぎる不自然さ”が、やがて正体を暴いた。この動画はAIによって生成されたものだったのだ。

なぜこの映像は「騙せた」のか?
ここまで巧妙に人間の目を欺くAI動画はなぜ誕生したのか? その背景には2つの要因がある。
まず第一に、“夜間監視カメラ”という設定が絶妙だった。暗視モードの監視映像は低解像度・グレースケール・ノイズまみれ。つまり、AIが不得手とする高精度なディテール描写を最初から求められない世界なのだ。
こうした映像では、輪郭の曖昧さやフレーム間のブレが「リアルさ」の演出になる。エッジの甘さや圧縮ノイズは、むしろリアリティを高めるベールとして働く。
そして第二のポイントは、モチーフの選定が秀逸だったこと。もしこれが人間の動作を描いた動画であれば、視聴者はより厳しく観察し、破綻に気づきやすい。だが、ウサギやクマといった可愛らしくも未知な動物の動作には、人間側の「こう動くはず」という先入観があまり存在しない。そのため、多少の違和感には気づきにくいのだ。

実際、同様のAI生成動画が続々と登場している。夜の裏庭でアライグマが自発的に増殖したり、クマが勢いよく跳ねた結果、トランポリンが破裂するシーンなど、ユーモアと異常さが紙一重な映像たちが出回っている。

この技術の正体──Veo3か?
では、この映像を作り出したAIは何なのか? 現段階では制作元も使用されたモデルも明らかにされていない。しかし、多くのユーザーがその生成能力の高さからGoogleが開発した「Veo3」を使用した可能性を指摘している。
Veo3は、短い動画(最大10秒程度)を高精度に生成できる最新のAI動画生成モデルだ。その生成物は、カメラの特性(ブレ・圧縮・光の反射)まで計算に入れた描写が可能であり、今や“リアルと見まがう”レベルに到達している。
実際、筆者もVeo3を用いてウサギのジャンプ動画を試作してみたが、やはりクオリティの高さには驚かされた。ただし、公開された5億再生動画のレベルには一歩及ばなかった。おそらく、提示プロンプトやトレーニングデータの工夫が功を奏していたのだろう。
笑える時代は終わり? 「次は詐欺が始まる」
2023年頃のAI動画といえば、“奇妙な魅力”を持つコンテンツが主流だった。たとえば、AIが生成したウィル・スミスのラーメン食べシーン。麺が顔を貫通し、咀嚼もカクカクとぎこちない。見て笑える、いわば“ネタ動画”の域だった。
だが、たった2年で情勢は大きく変わった。AIは今や、「笑わせる」ではなく「信じ込ませる」フェーズに突入している。
これは単なるSNS映えではない。フェイクニュース、詐欺、なりすまし——その起点になり得る。実際、多くのユーザーがこの動画を「実際の監視映像」と信じ込み、友人とシェアしていた事実がある。もはやこれは“エンタメ”の枠を越えている。
AIフェイク動画を見抜くために
今後、AI動画がますます精巧になる中で、私たちはどう身を守るべきか? 筆者が推奨したい2つの簡単なチェックポイントがある。
ひとつは、投稿者がAI関連のタグやキーワード(#AI, #生成動画など)を使っているかを確認すること。もうひとつは、動画の長さ。現在トップクラスの生成ツールでも、高品質な出力は10秒以内が限界だ。これ以上の長尺は、まだ不自然さが出やすい。
結びに:トランポリンの上にいたのは、現実か、幻か
5億回も再生されたこの“ウサギ動画”は、単なるバズコンテンツではない。AIのリアリティ表現がここまで来たこと、そしてそれをどう受け止めるかという課題を、私たちに突きつけている。
次にあなたのスマホに届く動画。それは本当に「現実」か?
私たちは今、“見たものを疑う”スキルを学ばなければならない時代に突入しているのかもしれない。