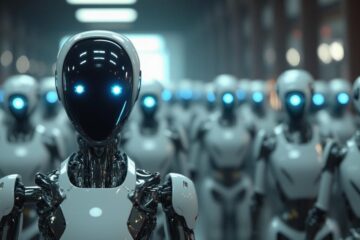バブアニューギニアの密林地帯。湿った空気を裂いて響く部族の声。その声には、我々が知っている「心から愛してる」という表現は存在しない。彼らは感情の中心を「心」ではなく「肝臓」に置く。想いを伝えたいとき、彼らは「肝臓を開け」と語る。
そして、その同じ島の別の部族、ラワ人にとっての感情の座は胃にあるという。
この極めて文化的、かつ人間的なニュアンスの違いが、いまAI翻訳の限界として立ちはだかっている。
忘れ去られた「語り」の荒野
大規模言語モデル、たとえばChatGPTやGeminiなどは、いまや私たちの日常にすっかり溶け込んでいる。しかし、これらのAIは英語という豊富なデータに支えられた富裕層のような言語でしか、その力を存分に発揮できない。
現実として、AIのトレーニングデータの90%以上は英語に偏っている。その結果、AIの言語理解は英語的論理に深く依存することになる。
たとえば、中国語の成句を入力したとき、AIはそれをまず英語に翻訳し、その意味を想定し、再び目に見えない手順で原言語に戻す。この過程で、ニュアンスや文化背景は簡単に霧散してしまう。
そして、さらに厳しい現実がある。
アワ語のような話者が数千人しかいない「低資源言語」に至っては、そもそもインターネット上に存在する文書がほとんどない。つまり、AIには読むべき本すら存在しないのだ。
Metaの挑戦——「取り残さない」AI
2022年、Metaは「No Language Left Behind(NLLB-200)」という多言語翻訳モデルを公開した。この名の通り、「どの言語も取り残さない」ことを理念とするモデルだ。ザッカーバーグの本意が広告収益の最大化だったにせよ、この技術は思わぬ形で言語学の世界に革命を起こした。
このモデルは、多くのマイナー言語の翻訳作業を機械的にブーストさせ、さまざまな翻訳機関に取り入れられた。だが、喜ぶのはまだ早い。
AIには、避けられない弱点がある。それは、「嘘をつくこと」だ。
AIの嘘——幻覚という名前の間違い
データサイエンティストのダニエル・ウィットナックが指摘するように、AIは知らない分野に直面しても、黙って黙考することができない。代わりに、それらしく「もっともらしい嘘」を生成してしまう。これが、いわゆる「AI幻覚」と呼ばれる現象だ。
たとえば、新約聖書には「epiousion(エピウーシオン)」という語がある。2000年近く、学者たちはこの単語の意味を解明できていない。それでもAIは、確率的に最も通りの良い単語を推測し、そこに「日常の糧」などと訳語を当てる。本質を理解しないまま、もっともらしい答えを返すのだ。
また、「振動性幻覚」や「分離性幻覚」と呼ばれる症状も確認されている。AIが同じ単語を延々と繰り返したり、原文と無関係な内容を創作してしまう現象である。たとえば、エコロジー(eco-friendly)を「経済的」(econ-friendly)と誤訳するような誤りも、商業文書であれば問題程度で済む。しかし、文化や宗教、法律に関わる文書でこのような間違いが起きた場合、その代償は致命的だ。
感覚なき翻訳者——AIの肉体なき限界
AIには「身体」がない。だから、言葉の裏にある身体感覚や感情のリアリティを理解できない。
ナミビアのルクワンガリ語には、「Hanyauku(ハニャウク)」という単語がある。これは「熱い砂の上をつま先で歩く」という感覚的な行為を意味する。しかし、サーバールームに生きるAIにとって、それはただの意味不明なデータ列にすぎない。
また、「攻城槌(バッタリング・ラム)」のような単語も、平和な部族社会には存在しない概念だ。人間の翻訳者であれば、状況に応じて「城門を壊すための巨大な木の棒」と意訳できる。だがAIは、それを逐語訳するか、意味を捨てて音訳するしかない。
つまり、AIは「人間の痛点や笑点」を理解できないのだ。
翻訳に残された最後の道——人間の役割
AIの驚異的な性能によって、聖書翻訳の工程は従来の10年以上から2年へと短縮された。IllumiNations(イルミネーションズ)という団体は、2033年までに全世界の言語で聖書翻訳を完了させるという野心的な目標を掲げている。
だが、AIが作るのはあくまでも「ドラフト」である。その先には、文化を理解し、文脈を読み解き、人間の感情を感じ取る存在——つまり人間が必要不可欠なのだ。
バブアニューギニアで「イエスを心に受け入れる」という表現を訳す際も、人間の翻訳者が「心」ではなく「肝臓」に翻訳し直す。このような「文化変換」は、いかなる高性能の演算力をもってしても再現不能である。
言葉という部族の迷路
翻訳とは、単なる言葉の変換ではない。それは文化、歴史、感情、身体感覚を含む人間的な体験の変換作業である。だからこそ、AIがどれほど発展しても、「最後の1マイル」は人間にしか歩めない。
たとえば、スコットランド語の「Tartle」は「紹介時に相手の名前を忘れる恥ずかしさ」を意味する。日本語の「教育ママ」は、「子供の教育に熱心すぎる母親」という文化的背景がある。そして、イタリア語の「Abbioccio」は、「満腹のあとの心地よい眠気」という、食文化に根差した感情を表す。
これらの「翻訳不可能な単語」は、AIがいくら進化しても簡単には処理できない。なぜなら、そこには人間の暮らしと感性、喜怒哀楽が染み込んでいるからだ。
私たちはいま、言葉を越えた理解の手段としてAIに期待を寄せている。その試みは、テクノロジーと人間の知性の協働による希望の象徴でもある。しかし、言葉が持つ本当の力——それは、感情と身体の記憶に支えられた、私たち自身の経験そのものである。
翻訳の未来は、AIと人間が手を取り合うことでしか切り拓けない。 最後の1マイル、それは肝臓の奥にある、言葉にならない想いの領域なのだ。