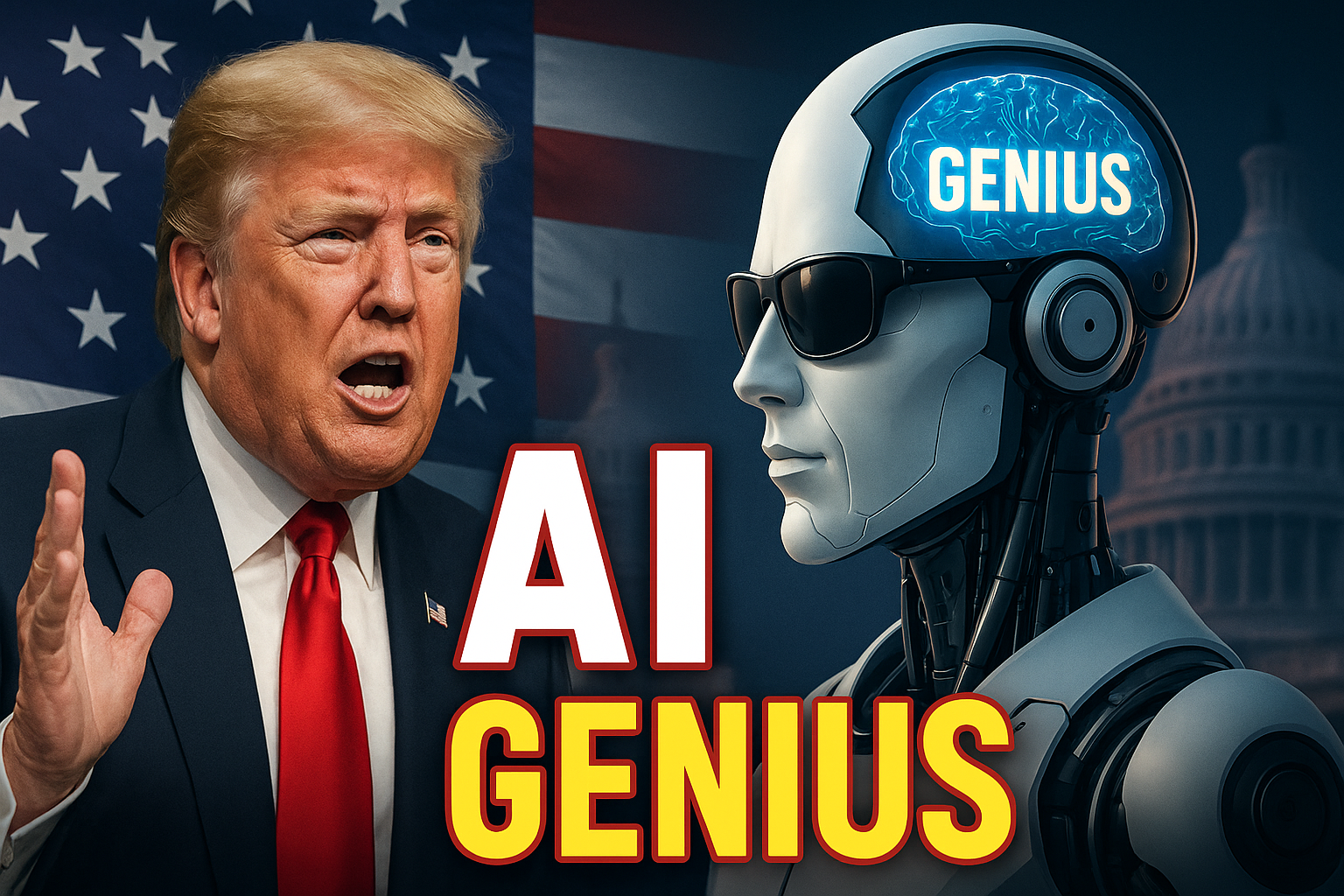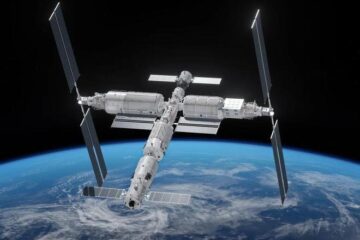人工知能(AI)という名称は、時代遅れなのかもしれない。少なくとも、ドナルド・トランプ前大統領にとっては。
2025年7月23日、ワシントンD.C.で開催されたAIサミットでの彼の発言が、再びメディアとテクノロジー界に大きな波紋を呼んでいる。
“人工”が気に食わない男、トランプ登壇
この日、壇上に現れたトランプ氏は、満席の聴衆の前で冒頭から強烈な一言を放つ。
「Artificial Intelligence(人工知能)という言葉が嫌いだ。人工的なんて言葉は受け入れられない。」
AI技術がもたらすインパクトや可能性に満ちたこのイベントで、話題は予想外の方向へと進んだ。トランプ氏は続けて、「この技術は“人工”ではなく、“天才”によるものだ」と主張。彼が提案した新たな名称は、なんと「Genius Intelligence(天才知能)」。
彼のこの突飛とも思える提案に、会場の一部では笑い声も上がったが、本人はいたって真剣だった。
「これは真面目な提案だ。私は“人工”という言葉が持つ響きが嫌いだ。それは何か偽物のように聞こえる。」
この一連の発言は、彼がかねてから用いてきた“Genius”というワードに対する執着を、改めて浮き彫りにした。
“Genius”という言葉に込められた政治的ブランディング
トランプ氏が“Genius”を好むのは、単なる言葉の好みではない。彼の政治スタンスや自己ブランディング戦略にも深く関係している。
「私はただ賢いんじゃない、“天才”なんだ」
これは2018年、彼がツイッターで自らを「非常に安定した天才(a very stable genius)」と形容した際の言葉だ。当時、トランプ氏の精神状態や知能を巡る議論が過熱していた中での強烈な自己主張だった。
さらに、彼は2025年7月中旬にも《Genius Act(天才法案)》と題された法案に署名。この法案は、米国のステーブルコイン開発を支援する枠組みを構築する内容だったが、そのネーミングには明らかに意図的な“Genius”の使用が見て取れる。
エロン・マスクに対しても、かつては「スーパー天才」と絶賛していたが、関係が冷却した後でも「半分は天才、半分は子供」と表現するなど、“天才”という評価軸は彼の語録において特別な意味を持っているようだ。
ホワイトハウスのAI戦略、「天才知能」構想の本気度
奇抜な名称変更提案の裏で、トランプ政権はAI分野で具体的な国家戦略を着々と進めている。彼の発言に先立ち、ホワイトハウスは「人工知能行動計画(AI Action Plan)」を正式に発表した。
この計画は以下の3本柱から構成されている:
-
AI技術革新の加速
-
国内AIインフラの強化
-
アメリカ製のハードウェア・ソフトウェアを世界標準に
さらに、注目すべきは以下の文言だ。
「すべての連邦政府調達における大規模言語モデルは、客観性を持ち、トップダウン的なイデオロギーの影響を受けてはならない。」
つまり、政権はAIの中立性・政治的偏り排除を政策として明言しているのだ。
その上で、トランプ氏は演説中にこう宣言した。
「アメリカ政府は、真実を擁護するAIだけを使う。“Woke(覚醒主義)”を今すぐ排除せよ!」
この「反Woke」路線は、近年の保守派政治に共通するテーマであり、AI技術においても文化戦争の延長線上にあることを印象付ける。
「勝利宣言」から見え隠れする米中AI覇権戦争
サミットの締めくくりで、トランプ氏は再び会場のテックリーダーたちに向けて一言。
「幸運を祈る。だが、この戦いは今始まったばかりだ。そして我々は勝つ。」
この言葉の裏には、単なる国内政策ではなく、米中を中心としたAI覇権争いへの強い意識がある。
実際にトランプ氏は演説中、AIのリスクにも言及しつつ、「危険だからといって手放すわけにはいかない」と強調。競争を放棄することは国益に反すると明言した。
また、署名された2つの大統領令の中では、自動署名機を使わないという発言でバイデン前大統領を皮肉る場面もあり、そこにも“人間味”や“直筆”といった価値観が現れているのが印象的だった。
総括
トランプ氏の「AIは人工ではなく天才の産物だ」という発言は、単なる奇抜なアイデアにとどまらず、AIをめぐる政治的、倫理的、そして国際的な競争の象徴でもある。
名称の変更提案から法案のネーミングに至るまで、全てに“Genius”という言葉を埋め込む彼の戦略は、政治家としての嗅覚とブランディング力の表れだろう。
果たしてこの「天才知能」は、単なる言葉遊びで終わるのか? それとも、米国のAI戦略を象徴するキーワードとして定着していくのか?
今後の動向に注目したい。