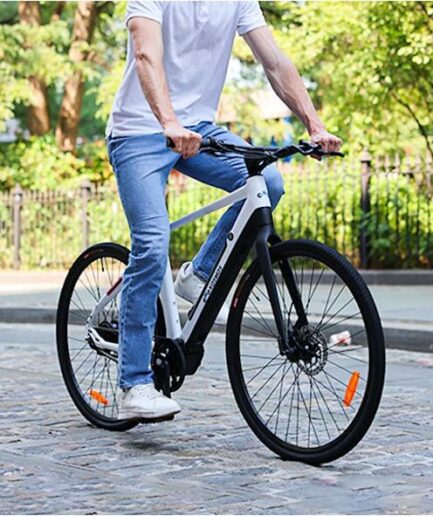2025年3月末、OpenAIがChatGPTに新たな画像生成機能を追加したことで、世界中のSNSが一斉に盛り上がった。その盛り上がりの中心にあったのが、**「ジブリ風AI画像」**だ。
自撮り写真をアニメタッチに変換する遊びが爆発的に広がり、とりわけ宮崎駿監督率いるスタジオジブリの特徴的な2Dアニメスタイルを模した画像が、X(旧Twitter)やInstagramで次々と投稿された。この流行は一時的なブームを超え、デジタルアートと著作権の根本的な議論へと飛び火することになる。
オルトマンCEOも巻き込まれた「ジブリ風アバター」騒動
火種となったのは、OpenAIのCEOサム・オルトマン自身が、Xのプロフィール画像をジブリ風AIイラストに変更したことだった。
ChatGPTの最新モデル「GPT-4o」は、テキスト入力からの画像生成だけでなく、アップロード画像のスタイル変換にも対応している。しかもその変換精度は格段に向上しており、ユーザーは簡単なプロンプトを使って、自分の顔写真をジブリ調のキャラクター風に変えることができる。

SNSには「となりのトトロ風自分」「ハウル風彼氏」などと称された画像があふれ、一種の「AI仮装パーティー」の様相を呈した。しかしこの華やかなブームの裏で、深刻な問題が同時に進行していた。
著作権問題とリソース問題──OpenAIが下した制限措置
画像生成機能のリリース直後から、ジブリファンやクリエイターの一部からは懸念の声が上がっていた。「これはジブリのアートを盗用しているのではないか?」
これに呼応するように、OpenAIは短期間のうちに以下の対策を発表した。
-
ChatGPTでジブリ風画像を生成するプロンプトは禁止
-
生成速度に制限を導入
-
無料ユーザーへの画像機能開放を延期
明言は避けられているが、ジブリ側からの直接的なクレームが存在した可能性も否定できない。また、想定以上のアクセス集中により、OpenAIのGPUリソースが逼迫し、一部のサービス低下も引き起こしていたという。

大学キャンパスにも波及、学生からの異論と憂慮
この話題は学術機関にまで波及する。アリゾナ州立大学(ASU)では、学内施設のPR用にジブリ風AI画像を利用したところ、学生たちから批判の声が上がった。
アリゾナ州立大学の副教授、ウェンディ・ウィリアムズ氏は次のように語っている。
「ジブリは、観る人に感情を伝える力のある作品を創り出してきた。そのスタイルは単なるビジュアルではなく、“魂”の表現です。」
彼女が問題視するのは、AI生成画像の「魂の欠如」である。たとえ見た目がジブリ風であっても、それは数値と計算によって作られたものであり、人間の感性や試行錯誤が宿る手描きのアニメーションとは本質的に異なるという。
若いアーティストたちの叫び:「AIは私たちの居場所を奪う」
アリゾナ州立大学大学1年生のハーレイ・ケインは、ジブリスタイルに憧れる一人だった。しかしAI画像が氾濫する現状に対し、複雑な思いを口にする。
「AIで何でも作れるようになると、私たちの努力の意味がなくなってしまう気がする。」
同じく新入生のマヤ・コロナド=ヘンソンは、さらに強い言葉で訴える。
「AIの作品には“愛”がない。アートとは、時間と情熱を注ぎ込んだ結果であって、それをショートカットすることは芸術の否定です。」
このような声は、単なる反AIではなく、“創作の尊厳”を守りたいという切実な叫びでもある。
技術と表現のバランス──真の創作とは何か?
AIが可能にする表現は年々進化している。MidjourneyやStable Diffusionといった画像生成AIは、かつては想像もできなかったレベルのビジュアルを、ほんの数秒で作り出す。
だが、AIがいくら「ジブリ風の絵」を生成できても、それは「ジブリの作品」ではない。キャラクターに宿る背景や、ワンカットごとの演出意図、色彩設計に込められた感情、すべてが異なる。
副教授ウィリアムズ氏は、こう締めくくっている。
「アニメーションとは、単なる視覚情報の集合体ではなく、創造という旅そのものなんです。」
AIアートがもたらす便利さの裏に、私たちは今一度、「創造するとは何か」を問う必要があるのではないだろうか。
終わりに──AIとアートは共存できるか?
ジブリ風AI画像の一連の騒動は、単なる“流行”として見過ごせるものではなかった。それは、今後AIが関わるあらゆる創作分野にとっての試金石でもある。
著作権の問題、表現のオリジナリティ、創作者の尊厳、観る側の共感。
この4つのバランスをどう取っていくかが、我々の“創作とAIの未来”を決めるのだ。
そして何よりも大事なのは、「誰がその作品を作ったのか」という問いに、胸を張って答えられる世界を守ることだろう。